11月8日は
【いい歯の日】🦷
🍁11月限定でデンタルキャンペーンを行います🍁
11月中に対象のデンタル製品をご購入した方に、嬉しいプレゼントをご用意しております!
ぜひこの機会に、歯ブラシの買い替えや新たなケア製品のお試しをされてみてはいかがでしょうか?

プレゼント内容
🐱ねこちゃん:デンタルちゅるっと1本プレゼント
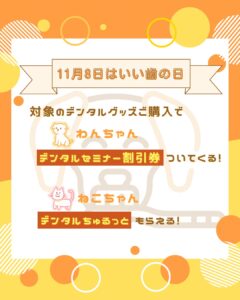
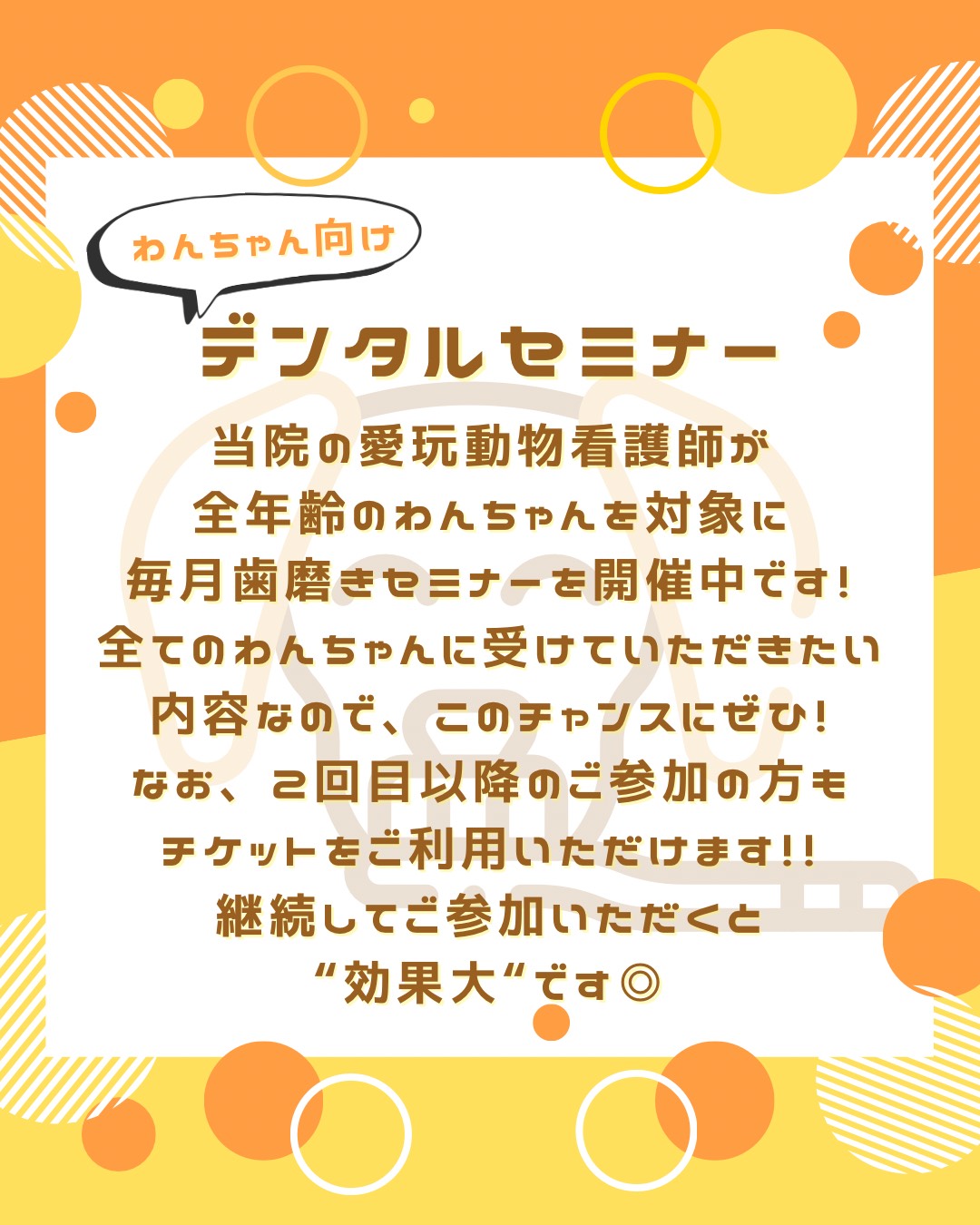
この機会にぜひぜひご参加ください😄
美味しく歯の健康をケアできる優れものです!お試しあれ!!

11月8日は
【いい歯の日】🦷
🍁11月限定でデンタルキャンペーンを行います🍁
11月中に対象のデンタル製品をご購入した方に、嬉しいプレゼントをご用意しております!
ぜひこの機会に、歯ブラシの買い替えや新たなケア製品のお試しをされてみてはいかがでしょうか?

プレゼント内容
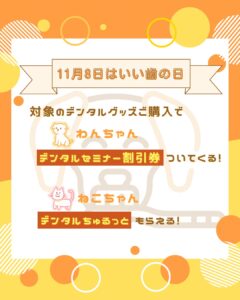
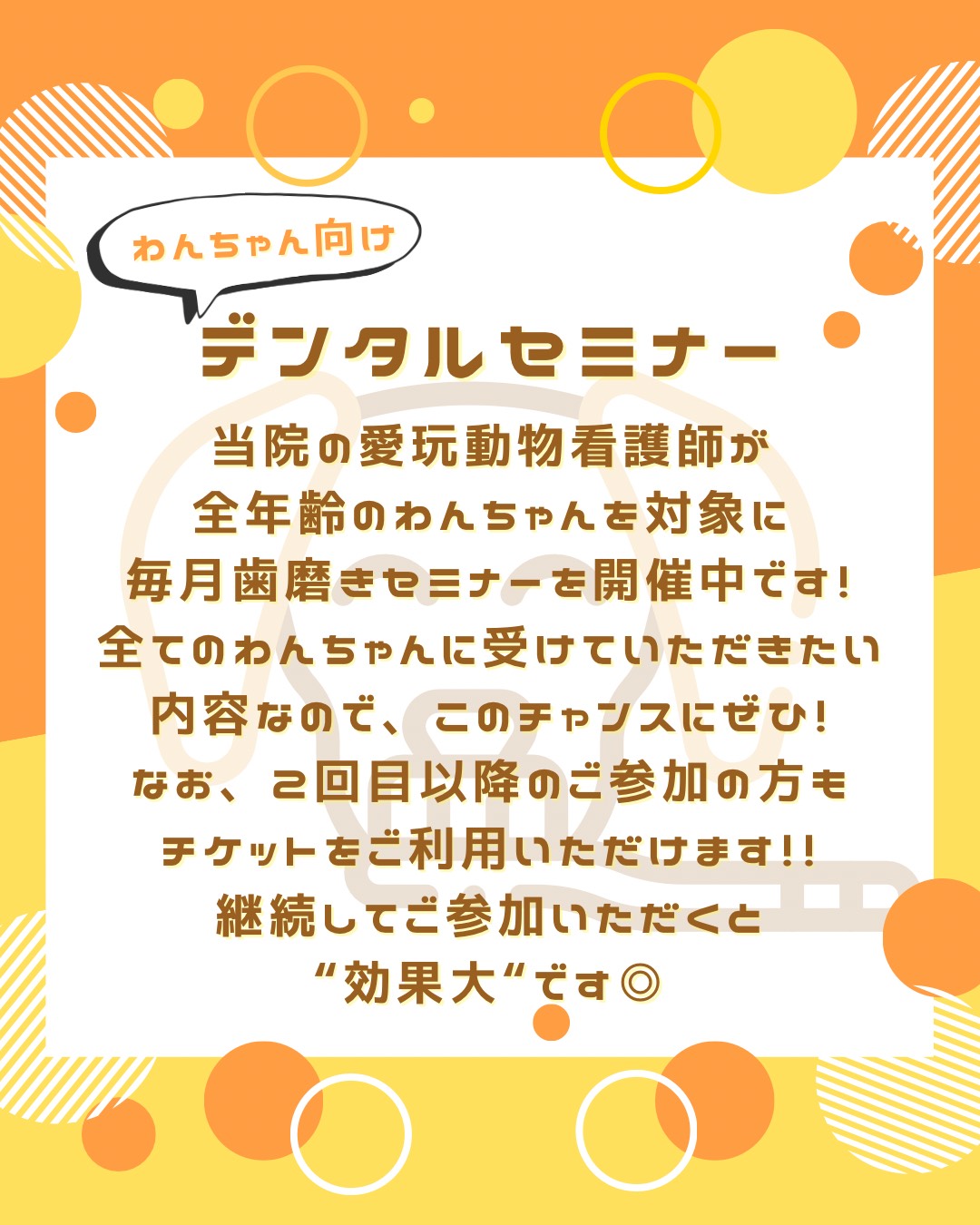

「猫の毛が円形に抜けている」
「猫が脱毛しているけど、感染症によるもの?」
「一緒に暮らす猫同士で脱毛がうつっている気がする」
猫に脱毛がみられると心配ですよね。
人にもうつるのか悩む方も多いかもしれません。
今回は脱毛の原因のひとつである猫のカビについて解説していきます。
ぜひ最後まで読んでいただき、猫に脱毛がみられるときの参考にしてください。

猫に脱毛がみられたときに考えられる原因は、以下のようにさまざまです。
・感染症(細菌、真菌、寄生虫によるもの)
・アレルギー
・ホルモン性疾患
・自己免疫性疾患
・腫瘍
上記以外にもストレス性や代謝性など、脱毛が起こる原因は多岐にわたります。
今回は、感染症のなかでも人にうつる可能性の高い猫カビについて解説していきます。
猫に脱毛がみられたときに原因のひとつとして考えられるのが猫カビです。
猫カビは正式には皮膚糸状菌症という、真菌(カビ)による感染症のことです。
真菌にはさまざまな種類がありますが、そのうちの数種類のカビが猫カビの原因となります。
感染している犬や猫との接触が原因となるため、以下のような猫で感染の可能性が高いです。
・ペットショップ・ブリーダーから迎え入れたばかりの子猫
・外に出る猫
・多頭飼育の猫
免疫力が低いと感染するリスクが高く、子猫や免疫不全状態の猫ではとくに注意が必要です。
毛に付着して感染することから長毛の猫でもよくみられます。
長毛の猫だと、毛に隠れて皮膚症状が見えにくいため、ブラッシングの際など日頃から皮膚の状態も合わせて観察することがおすすめです。
また、カビに感染していたとしても症状が出ないケースがあります。
症状が出ていない猫でも皮膚糸状菌に感染していれば、接触で他の動物に感染するので注意が必要です。
真菌は感染力が強く、中途半端な対応だと再感染の可能性があります。
治療と合わせて生活環境のクリーニングも同時並行で行うことが大切です。
猫カビになると、顔まわりや足先・尻尾の先などに以下のような症状がみられます。
・脱毛
・赤み
・フケ
・痒み
これらの症状は左右非対称に出てきます。
痒みはほぼない場合もあり、あったとしても脱毛の割に痒み自体は軽度の場合が多いです。
猫カビが人間に感染した場合は、腕などに円形の赤い発疹が出たり、痒みが出たりします。
猫カビの治療中に人間にも症状が出た場合は、人間の皮膚科で診療してもらいましょう。
その際は猫が皮膚糸状菌症になっていることも合わせて伝えてください。
猫がカビと診断されたときに自宅でできることは感染源との接触を防ぐことや、生活環境を綺麗にすることなどです。
動物病院での治療に合わせて自宅での対策も行いましょう。
感染源との接触を防ぐ
感染源となり得る外に出る猫や、野良猫との接触は感染リスクを高めるので避けましょう。
多頭飼育の場合、猫カビに感染している猫はなるべく隔離することをおすすめします。
可能な範囲で、移動も少なくできるとより良いです。
猫カビは動物間だけでなく、動物と人の間でも感染します。
感染している猫に触れたあとは手だけでなく、腕などもよく洗いましょう。
服などに着いた感染猫の抜け毛が、他の猫に着くことで感染が蔓延することもあるので注意が必要です。
また、感染している猫以外にも、感染猫の毛が付着していそうなものは感染源となります。
毛布やクッション、ブラシやバリカンなども感染源になる可能性が高いです。
生活環境を綺麗にする
生活環境を綺麗にすることも猫カビの対策として重要です。
皮膚糸状菌は生命力が強く、自宅内で1年間も生き残ることができると言われます。
抜けた毛も感染源になるため、掃除をしないと再び感染してしまいます。
掃除機や使い捨てシートなどで床を綺麗にし、消毒液を使用して掃除しましょう。
毛布やクッションなど洗えるものはなるべく塩素系の消毒液につけてから洗濯することをおすすめします。
免疫力の維持
猫カビの感染は免疫力の低下にも関係しています。
基本的に子猫など免疫力の低い猫で感染しやすい皮膚糸状菌ですが、免疫力が下がると成猫でも感染します。
免疫力維持のために日頃から以下のようなことに気をつけてみてください。
・ストレスの少ない生活環境
・適度な運動
・バランスの良い食事
人間も猫と同様、免疫力が低いと感染しやすいです。
子供や高齢者、治療中の疾患がある人などはとくに感染のリスクが高いため、感染している猫とのスキンシップは控えることをおすすめします。
猫のカビと言われる皮膚糸状菌は、主に感染動物との接触でうつっていきます。
野良猫との接触や、外に出る猫の場合はとくに注意が必要です。
脱毛や痒みなど心配な症状がみられたら動物病院でみてもらいましょう。
猫のカビは人にも感染するため、人に赤みや痒みなどの症状が出た場合は人間の病院でみてもらってください。
皮膚糸状菌は主に毛に付着し、抜け毛も感染源となります。
一度症状が治っても、環境が綺麗になっていないと何度も再感染する可能性があります。
カーペットやブラシなど毛が付着しそうなものは全て綺麗に掃除しましょう。
「猫が脱毛していてカビかもしれない」とお悩みの際はお気軽にご相談ください。
大阪市城東区鶴見区の動物病院
城東鶴見どうぶつ病院
「散歩中たまにスキップしていて後ろ足の動きが変」
「まだ若いのに後ろ足を痛がって、足をあげることが多い」
「チワワを抱っこしていたら落としてしまって後ろ足をあげている」
若いチワワを飼っていてこのような症状が見られると心配ですよね。
「元気だし病院に行かなくても大丈夫」と放っておくと、さまざまな疾患を見逃してしまう可能性があります。
今回は若いチワワが後ろ足を痛がっているときに考えられる疾患について解説します。
ぜひ最後までお読みいただき、若いチワワが後ろ足を痛がっているときにお役立てください。

若いチワワが後ろ足を痛がっているというだけではどのような状態なのか判断が難しいため、早期に病院を受診しましょう。
犬が後ろ足を痛がっている場合、さまざまな原因が考えられます。
人間でいう捻挫のように様子を見ていて治るような状態の可能性や、手術が必要な病気の可能性もあります。
元気も食欲もあるからと言って一概に様子を見ていて大丈夫とは言い切れません。
犬が後ろ足を痛がるとき、動物病院では以下のような検査が行われます。
・視診・歩様検査:立ち方、歩き方を確認することで痛みのある足を確認
・触診:全身の骨や関節を念入りに触診し、痛みや構造的な異常を確認
・X線検査:異常が認められた箇所のX線検査を実施することで骨折や脱臼、関節炎などを確認
これらの検査を実施することで、痛がっている箇所や原因について調べることができます。
神経疾患によって後ろ足の異常が認められることもあるため、必要に応じて神経学的な検査が実施されることもあります。
若いチワワが後ろ足を痛がるときに考えられる原因はさまざまです。
しかし、若齢かつ小型犬となるとある程度疾患は限られてきます。
以下に可能性の高い疾患を解説します。
膝蓋骨脱臼(パテラ)
膝のお皿である膝蓋骨は英語でパテラと言われるため、膝蓋骨脱臼はそのままパテラと呼ばれることが多いです。
パテラはチワワやトイプードルなどの小型犬で多く認められる疾患です。
膝蓋骨が本来あるべき場所(大腿骨の滑車)から脱臼してしまう病気で、重症度は4段階に分類されます。
・Grade1 膝蓋骨は手で押すと脱臼するが、手を離せば正常な位置に戻る
・Grade2 膝蓋骨は膝を曲げると自然に脱臼や整復を繰り返す
・Grade3 膝蓋骨は常に脱臼していて、手で押せば整復できる
・Grade4 膝蓋骨は常に脱臼していて、手で押しても整復されない
Grade1が最も軽度、Grade4が最も進行した状態です。
散歩中に急にケンケンするように歩いたり、後ろ足を完全に挙げてしまったりと症状はさまざまです。
触診によって重症度が評価され、X線検査で骨の変形や関節炎の有無が確認されます。
治療法は内科的な治療と手術による整復があり、重症度や症状によって治療法が検討されます。
レッグ・カルベ・ペルテス病
レッグ・カルベ・ペルテス病は股関節の大腿骨頭が壊死してしまう病気で、原因ははっきり分かっていません。
1歳未満の若齢かつ小型犬に多く発生し、壊死した大腿骨頭は激しい痛みが生じるため跛行の原因となります。
進行すると筋肉量が低下し、足をほとんど使えなくなってしまうことが多いため早期の診断が重要です。
触診では筋肉量の低下や股関節の痛みが確認され、X線検査で診断されます。
壊死した大腿骨頭が内科的に修復されることは難しく、ほとんどの症例で手術が必要になります。
骨折
後ろ足の骨折は骨のさまざまな場所で起こります。
若い犬ではとくに骨の成長を担っている、成長板での骨折が起こりやすいです。
成長板は軟骨性の組織で、柔らかく脆弱なため頻繁に骨折がみられます。
ソファからの着地失敗や抱っこからの落下など日常生活における小さな衝撃で骨折することもあるため注意が必要です。
成長板骨折が認められた場合は早期に整復手術が必要になります。
若いチワワが後ろ足を痛がっている場合、捻挫のような様子見で治るような状態から手術が必要になる病気までさまざまな可能性が考えられます。
「後ろ足を痛がっているけど若いし元気だから大丈夫」と様子を見ていると病気の発見が遅れてしまいます。
発見が遅れると治療に時間がかかってしまうため早期の診断・治療が重要です。
若いチワワが後ろ足を痛がっている場合は早めに病院を受診しましょう。
犬が足を痛がっていてお悩みの際はお気軽にご相談ください。
大阪市城東区鶴見区の動物病院
城東鶴見どうぶつ病院
「精巣の大きさが左右で違う気がする」
「去勢をするかずっと悩んでいるけど将来精巣腫瘍になっちゃうの?」
「お腹の中に精巣が残っているけど大丈夫?」
犬の去勢をしていなかったり、犬の精巣や身体に異変があると心配になる方も多いのではないでしょうか。
今回は犬の精巣腫瘍について解説していきます。
ぜひ最後までお読みいただき、犬の精巣に異変を感じたときや去勢を検討しているときに参考にしてみてください。

犬の精巣腫瘍とは、オス犬の生殖器のひとつである精巣が腫瘍化してしまうものです。
去勢をしていない犬のうち、とくに中齢〜高齢犬で多いです。
未去勢犬の約30%で腫瘍化するという報告もあります。
精巣腫瘍は主に以下のような種類に分けられます。
・間質細胞腫(ラディッヒ細胞腫)
・精上皮腫(セミノーマ)
・セルトリ細胞腫
上記の腫瘍が組み合わさった混合腫瘍が見られることも珍しくありません。
犬の精巣が腫瘍化してしまうと以下のようなことが起こる可能性があります。
精巣の大きさの違い
犬の精巣腫瘍では左右の精巣の大きさに差が出ます。
精巣腫瘍の多くは片側で発生しますが、両側に発生することもあります。
この場合は精巣が通常よりも大きかったり硬くなっていたりすることで気がつくことが多いです。
左右差がないからと言って精巣腫瘍ではないとは限らず、注意が必要です。
性ホルモンの過剰分泌
精巣腫瘍の種類によっては、性ホルモンが過剰に分泌されることで出てくる症状もあります。
とくにセルトリ細胞腫ではエストロゲンという性ホルモンが過剰分泌され、以下のような症状がみられることがあります。
・脱毛
・色素沈着
・乳腺の肥大
・腫瘍と反対側の精巣の萎縮
・貧血
・血小板の減少
性ホルモンの過剰分泌により骨髄で血液成分を作る働きが抑制されることもあります。
骨髄の働き抑制に伴って起こる貧血や血小板の減少などが重度になると、命に関わります。
転移
精巣腫瘍は1〜20%ほどの確率で他の臓器に転移します。
リンパ節から、肝臓・腎臓・肺・脳など様々な場所へ転移の可能性があります。
転移先により症状もさまざまです。
例えば肺に転移すれば咳が出たり、呼吸が苦しそうなどの症状がみられるでしょう。
精巣は成長するにつれて、お腹の中からお腹の外にある陰嚢という袋に入るように下降するのが正常です。
しかし下降せずにお腹の中に残っていたり、鼠蹊部あたりで留まってしまう場合があります。
これを潜在精巣と言い、通常の精巣よりも精巣腫瘍になる可能性が約10倍にもなります。
潜在精巣の場合は早期発見・早期治療のために、超音波検査や触診など動物病院での定期的な検査がおすすめです。
犬の精巣腫瘍の予防は、若いうちの去勢手術が有効です。
とくに、潜在精巣は通常よりも精巣が腫瘍化する確率が高いため、早めに手術してしまうことをおすすめします。
若いうちに去勢手術を行うことには精巣腫瘍の予防以外にも様々なメリットがあります。
去勢手術のメリットについてはこちらをご覧ください。
犬の去勢をするメリットは?どうして動物病院では去勢が勧められるのか
精巣腫瘍は去勢をしていない中高齢の犬でよくみられます。
精巣腫瘍になると精巣の大きさや硬さの違和感や脱毛などで気がつくこともあるでしょう。
小さな変化でもすぐに気がつけるよう、日頃からよく犬を観察しておくことがおすすめです。
精巣腫瘍を放置してしまうと骨髄の働きが抑制されるなど、重症化する可能性もあります。
最悪の場合、命に関わりますので予防が大切です。
精巣腫瘍は若いうちに去勢手術をすることで予防できる病気です。
犬の精巣腫瘍や去勢でお悩みの際はお気軽にご相談ください。
大阪市城東区鶴見区の動物病院
城東鶴見どうぶつ病院
「猫のおしっこが昨日から出てない気がする」
「トイレに行くけどおしっこが確認できない」
「猫のおしっこが出ないときは動物病院に行った方が良いの?」
猫のおしっこが出ないと、動物病院に行った方が良いのか悩んでしまいますよね。
実は、猫のおしっこが全く出ないのは命に関わる緊急事態です。
今回は猫のおしっこが出なくなる原因や危険性などについて解説していきます。
ぜひ最後まで読んでいただき、緊急時の参考にしてください。

猫のおしっこは全く出ていないのか、少しずつでも出ているのかによっても危険度は異なります。
猫の状態が以下のどれに当てはまりそうか今一度確認してみましょう。
・トイレに行くがおしっこの量が少ない
・実はトイレ以外の場所でおしっこをしている
・何度もトイレに行くのにおしっこが全く出ていない
一番最後のおしっこが全く出ない状況だと非常に危険です。
すぐに動物病院へ行きましょう。
猫のおしっこが出なくなる主な原因は、尿道が詰まってしまう尿道閉塞です。
尿道は、腎臓で作られたおしっこが膀胱にためられ、膀胱から身体の外に排泄するときの通り道です。
とくにオス猫では尿道が細長く、メス猫よりも尿道が詰まりやすい傾向があります。
尿路結石や膀胱炎などが原因となって、結石や炎症により尿道が塞がれ、おしっこを排泄することができなくなります。
尿道閉塞は、おしっこを排泄することができず体内に毒素が溜まっていく危険な状態です。
そのまま時間が経過していくと、急性腎不全に陥ります。
するとおしっこで排泄される予定だった毒素がどんどん体内に溜まっていき、意識障害や不整脈を起こして最悪の場合死にいたります。
尿道閉塞が起こっている場合、トイレで力んだり、苦しそうにしたりするなどに加えて以下の症状もみられることがあります。
・排尿痛
・元気消失
・食欲不振
・嘔吐
尿道が閉塞していても膀胱が限界を迎えると、ポタポタとおしっこが滴る可能性もあります。
おしっこがほんの少し出ていても尿道閉塞の場合がありますので、気になる症状がみられたときは早めに動物病院へ行きましょう。
猫のおしっこが出ていなかったり、気になる症状がある場合はすぐに動物病院へ行きましょう。
非常に危険な状態なのでかかりつけの動物病院が休診日だったとしても、次の日や朝まで待たずに、そのときに行ける病院へ行くことをおすすめします。
自宅で無理に膀胱を刺激したり、圧迫したりすることはやめましょう。
痛みが増したり、最悪の場合膀胱が破裂すると命を脅かす可能性もあります。
猫のおしっこが出ないときは尿道が閉塞していて非常に危険な状態の可能性があります。
すぐに動物病院に連絡しましょう。
猫の症状に気づくためにも、毎日排泄の様子をよく観察することが大切です。
もしかしたらこっそりトイレ以外の場所で排泄していることもありますので気をつけて確認しましょう。
血尿や頻尿など膀胱炎のような症状が出ていたら、動物病院で治療するようにしましょう。
「たかが膀胱炎」と放置してしまうと尿道閉塞のような、危険な状態に繋がってしまうこともあります。
猫のおしっこで気になる症状があってお悩みの際はお気軽にご相談ください。
大阪市城東区鶴見区の動物病院
城東鶴見どうぶつ病院
「犬が寝ている時に大きないびきをかいている」
「短頭種を飼っているけど、散歩中に呼吸が荒くて心配」
「興奮するとゼーゼーと苦しそうな音を立てる」
こんな症状が頻繁に見られたら不安になりますよね。
今回は短頭種で見られる短頭種気道症候群について解説します。
ぜひ最後まで読んでいただき、犬の呼吸が苦しそうなときに役立ててください。

短頭種とはいわゆる鼻ぺちゃ犬種です。
頭蓋骨の長さに比べて鼻の長さが極端に短い犬のことで、以下のような犬種が当てはまります。
・パグ
・フレンチブルドッグ
・シーズー
・ボストンテリア
・ペキニーズ
短頭種は頭部の特殊な構造から呼吸器系の疾患にかかりやすいです。
短頭種は以下のような特徴的な構造がみられます。
・外鼻孔狭窄:外見上、鼻の穴が狭い
・軟口蓋過長:喉の奥の部分(軟口蓋)が長すぎる
・気管低形成:気管が細いなど
上記は特徴的な構造の一部ですが、これらが複合的に組み合わさって起こる気道閉塞がまとめて短頭種気道症候群と呼ばれます。
短頭種気道症候群では以下のような症状が見られます。
・大きないびき
・睡眠時呼吸障害
・異常な呼吸音
・チアノーゼ
・失神
上記以外にも運動するとすぐに息が切れたり、悪化すると急性の呼吸困難に陥ったりすることもあります。
暑い日や興奮時は熱中症になるリスク、中高齢になると突然死を起こすリスクもあります。
これらの症状が見られたときは、「短頭種だから仕方ない」と放っておくのではなく一度動物病院に相談してみると良いでしょう。
短頭種気道症候群は先天的な構造異常によるもので、完治は難しいです。
しかし外科手術によって症状の改善や、進行を遅らせることはできます。
症状が軽度であれば日常生活を整えることである程度症状の軽減も可能です。
基本的に以下のような対策や治療が勧められます。
日常生活を整える
短頭種気道症候群の場合、失神や呼吸困難など重度の症状が出てくることもあります。
日常生活で呼吸が苦しくなるような要因はなるべく取り除いてあげましょう。
とくに以下のようなことに注意することが大切です。
▶︎体重管理
短頭種気道症候群の症状軽減に重要なポイントのひとつが体重管理です。
肥満だと首周りにも脂肪がつき、ただでさえ狭い気道をさらに圧迫してしまいます。
適正体重を維持することで、呼吸が楽になる可能性もあるでしょう。
理想体型のチェック方法はこちらをご覧ください。
太っている?痩せている?犬の理想体型とは|犬の肥満度をチェック
▶︎温度調整
暑さに対する対策は必ず行うようにしましょう。
短頭種は鼻呼吸が十分にできないため体温調節が苦手で、熱中症のリスクが非常に高くなります。
とくに暑い時期の散歩は、早朝や夕方の涼しい時間帯に短時間で済ませるなどの対策を行いましょう。
▶︎過剰な興奮を避ける
犬を興奮させすぎないことも大切です。
激しい運動や長時間の遊びは避け、こまめに休憩を取りましょう。
チャイムや飼い主さまの帰宅など、いつ
も同じ刺激で興奮してしまうようならトレーニングを行うなどの対策がおすすめです。
▶︎ハーネスを使用する
犬のお散歩のときは首輪ではなくハーネスを使用しましょう。
首輪よりも気道への圧迫が弱く、気道への負担を軽減することができます。

内科治療
投薬や酸素吸入による一時的な症状の緩和は可能ですが、根本治療にはなりません。
症状が軽度のうちは内科治療で落ち着く可能性もありますが、早い段階から外科治療も検討しておくと良いでしょう。
外科治療
先天的かつ呼吸器系の複合的な異常なため、手術でも完治は難しいです。
しかし、手術を行った約90%で症状の改善が認められると言われ、病気の進行を遅らせる効果も期待されています。
短頭種気道症候群は基本的に進行性の病気で、進行していくと不可逆的な変化が起こる可能性があります。
そうなると手術しても症状が緩和されにくくなるため、手術内容は重症度などによっても異なりますが、若齢での手術が勧められています。
犬の短頭種気道症候群は、短頭種の特徴的な頭部の構造によって起こります。
様々な構造的特徴が組み合わさって起こる気道閉塞がまとめて短頭種気道症候群と呼ばれます。
手術で症状の改善は見込めますが、基本的に完治しない病気です。
体重管理や温度調節など自宅でできることもあります。
呼吸器系の症状が出るリスクを抑えるためにも日常生活や生活習慣を整えてあげましょう。
動物病院で定期的な健康チェックを受けることで、症状の進行を早期に発見することも可能です。
短頭種気道症候群でお悩みの際はお気軽にご相談ください。
大阪市城東区鶴見区の動物病院
城東鶴見どうぶつ病院
「犬が肥満じゃないか心配」
「大型犬なので自宅で体重を量ることが難しい」
「ダイエットさせたいけど、体重を量る以外の目安はないの?」
犬が健康に長生きするためにも体重管理は大切ですが、このように悩まれている飼い主さまも多いのではないでしょうか?
犬は犬種や年齢などによって理想体重が全然違い、どのくらいが健康的な体型なのか心配になりますよね。
今回は自宅でできる犬の理想体型のチェック方法について解説していきます。
ぜひ最後まで読んでいただき、犬の健康管理に役立ててください。

犬の理想的な体重は犬種などによって異なります。
犬が理想体型なのか、体重のみから判断することは難しいでしょう。
そこで動物病院でもよく使われるのがBCS(ボディコンディションスコア)という評価方法です。
BCSとはボディコンディションスコアの略で、5段階か9段階で評価される方法です。
見た目と触れた状態から体型、とくに脂肪の付き具合がチェックされます。
この評価方法だと犬種などに関わらず、犬が理想体型かを客観的に判断することが可能です。
自宅でできるBCSのチェック方法
BCSは見た目と触れた状態から判断するもので、自宅でも体型をチェックできます。
チェックするときのポイントは以下になります。
・肋骨が適度に触れるか
・上から見たときに緩やかなくびれがあるか
・横から見たときにお腹が引き締まっているか
まずは、両手で犬の胸の横を優しく触ってみましょう。
薄い脂肪の下に肋骨の感触が分かれば理想体型です。
肋骨が全く触れない場合は肥満、骨がゴツゴツと目立つ場合は痩せすぎの可能性があります。
次に、犬を立たせて真上から観察します。
胸から腰にかけて緩やかなくびれが見えるのが理想体型です。
くびれが全くない、または過度にくびれている場合は注意が必要になります。
最後に横から見て、お腹の吊り上がりをチェックします。
胸からお腹にかけて緩やかに吊り上がっているのが理想体型です。
お腹が垂れ下がっている、または極端に吊り上がっている場合は、体型に問題がある可能性が高いでしょう。

BCSを定期的にチェックすることで犬の健康管理にも繋がります。
太りすぎは関節や呼吸器に負担がかかったり、糖尿病になるリスクがあります。
痩せすぎの場合は食事量が足りていなかったり、病気で痩せてしまっている可能性があります。
自宅で体重を量ることが難しい大型犬や、抱っこでじっとしていられない犬などはBCSを健康管理に有効活用してみましょう。
犬の理想体型は犬種などによって異なります。
とくに体重を量れない犬はBCSを定期的にチェックすることがおすすめです。
理想体型から外れている場合は食事や運動などによる健康管理が必要です。
急激な体型の変化は病気の可能性もありますので、動物病院へ相談しましょう。
理想体型をキープすることが犬の健康にも繋がります。
犬の体重や体型でお悩みの際はお気軽にご相談ください。
大阪市城東区鶴見区の動物病院
城東鶴見どうぶつ病院
保護猫の譲渡会について

猫スマイルさん主催で保護猫の譲渡会を当院2階にて行います。



【入場料】500円(高校生以下は無料)
【日程】10月25日(土曜日)13時から15時
今後も偶数月第4週の土曜日に実施予定です。
【会場】当院2階
【予約】不要
【注意】
当日の体調により参加できない猫さんもいます。
譲渡には条件がございます。
当日猫さんを連れて帰ることはできません。
参加猫さんの詳細はInstagramをご覧ください。
【問い合わせ】
InstagramのDMから
もしくは
nekosmile222@gmail.com
にお願いいたします。



「猫の顎ニキビはどうやってケアすれば良い?」
「猫の顎にニキビができたけど人間の薬を使って良いの?」
「よく猫に顎ニキビができるので何か対策がしたい」
猫に何度も顎ニキビができてしまうことでお悩みの方も多いのではないでしょうか。
この記事では自宅でできる猫の顎ニキビのケアや対策について解説します。
ぜひ最後まで読んでいただき、猫の顎ニキビのケアに役立てていただけたらと思います。

ニキビは医学的にざ瘡と呼ばれ、猫の皮膚ではよく顎に発生することから顎ニキビと呼ばれることが多いです。
性別や品種・年齢などとは無関係にどの猫でも発症する可能性があります。
猫の顎に黒い粒のようなものがたくさん付着し、汚れていることに気づいて動物病院に相談する方が多いでしょう。
猫の顎ニキビの原因としては以下のようなことが関係していると考えられています。
・毛繕い不足
・皮脂の過剰産生
・ストレス
・免疫抑制
・細菌感染
明確な原因はわかっていませんが、他の猫にうつることはないので安心してください。
猫の顎ニキビは症状が軽度であれば、自宅でケアしてあげるだけで良くなる場合もあります。
しかし、細菌などによる二次感染が起こったり、慢性化して痒みが強くなってきたりすると抗生剤や薬用シャンプーなどで治療が必要な場合があります。
ケアの仕方が分からなかったり、状態が良くならないようであれば早めに動物病院に相談しましょう。
口の周りを清潔に保つ
猫の口周りを清潔に保つことは、顎ニキビの発生を防ぐことに繋がるでしょう。
口の周りは毛繕いがしにくく、汚れが溜まりやすいことも顎ニキビができやすくなる要因と考えられています。
食後に口の周りを優しく拭いてあげましょう。
温めたタオルや濡らしたコットンで清潔にしてあげた後に、乾いたものなどで拭くのがおすすめです。
湿ったまま放置せず、乾いた状態を保ってあげることも大切です。
食器を清潔に保つ
猫が使う食器を清潔に保つことも顎ニキビ対策として重要です。
プラスチックやステンレス製のものは汚れがつきやすく、雑菌が繁殖しやすいです。
ガラスや陶器のものを使用し、こまめに洗って清潔に保ちましょう。
ストレスの少ない生活環境を整える
猫の顎ニキビが発生する原因の一つとしてストレスが考えられているため、ストレスの少ない生活は猫の顎ニキビの予防にも繋がります。
環境の変化や多頭飼い、飼い主さまとのスキンシップ不足など、様々な原因でストレスを感じます。
引越しなどがあっても今まで使っていたトイレや毛布などは使えるようにし、落ち着ける場所を確保してあげましょう。
猫に人間のニキビ薬を使うことは控えましょう。
思わぬ副作用が出てくる場合がありますので、注意が必要です。
顎ニキビはどの猫にも発生する可能性があります。
軽症であればまず口周りや食器を清潔に保つことが大切です。
猫に顎ニキビができていなくても予防になるため、日頃からストレスの少ない、清潔な生活環境を保ちましょう。
猫の顎ニキビに対して人間の薬を使うと、思わぬ副作用が出てくる可能性があるため自己判断での使用は控えましょう。
ケアの仕方が分からなかったり、状態が良くならないようであれば早めに動物病院に相談することをおすすめします。
猫の顎ニキビのケアや治療でお悩みの際はお気軽にご相談ください。
大阪市城東区鶴見区の動物病院
城東鶴見どうぶつ病院