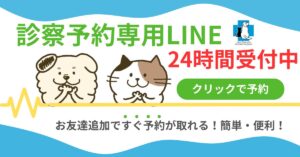「猫の毛が円形に抜けている」
「猫が脱毛しているけど、感染症によるもの?」
「一緒に暮らす猫同士で脱毛がうつっている気がする」
猫に脱毛がみられると心配ですよね。
人にもうつるのか悩む方も多いかもしれません。
今回は脱毛の原因のひとつである猫のカビについて解説していきます。
ぜひ最後まで読んでいただき、猫に脱毛がみられるときの参考にしてください。

猫の脱毛の原因は?
猫に脱毛がみられたときに考えられる原因は、以下のようにさまざまです。
・感染症(細菌、真菌、寄生虫によるもの)
・アレルギー
・ホルモン性疾患
・自己免疫性疾患
・腫瘍
上記以外にもストレス性や代謝性など、脱毛が起こる原因は多岐にわたります。
今回は、感染症のなかでも人にうつる可能性の高い猫カビについて解説していきます。
猫のカビとは?どうやってうつる?
猫に脱毛がみられたときに原因のひとつとして考えられるのが猫カビです。
猫カビは正式には皮膚糸状菌症という、真菌(カビ)による感染症のことです。
真菌にはさまざまな種類がありますが、そのうちの数種類のカビが猫カビの原因となります。
感染している犬や猫との接触が原因となるため、以下のような猫で感染の可能性が高いです。
・ペットショップ・ブリーダーから迎え入れたばかりの子猫
・外に出る猫
・多頭飼育の猫
免疫力が低いと感染するリスクが高く、子猫や免疫不全状態の猫ではとくに注意が必要です。
毛に付着して感染することから長毛の猫でもよくみられます。
長毛の猫だと、毛に隠れて皮膚症状が見えにくいため、ブラッシングの際など日頃から皮膚の状態も合わせて観察することがおすすめです。
また、カビに感染していたとしても症状が出ないケースがあります。
症状が出ていない猫でも皮膚糸状菌に感染していれば、接触で他の動物に感染するので注意が必要です。
真菌は感染力が強く、中途半端な対応だと再感染の可能性があります。
治療と合わせて生活環境のクリーニングも同時並行で行うことが大切です。
猫のカビではどんな症状が出てくる?
猫カビになると、顔まわりや足先・尻尾の先などに以下のような症状がみられます。
・脱毛
・赤み
・フケ
・痒み
これらの症状は左右非対称に出てきます。
痒みはほぼない場合もあり、あったとしても脱毛の割に痒み自体は軽度の場合が多いです。
猫カビが人間に感染した場合は、腕などに円形の赤い発疹が出たり、痒みが出たりします。
猫カビの治療中に人間にも症状が出た場合は、人間の皮膚科で診療してもらいましょう。
その際は猫が皮膚糸状菌症になっていることも合わせて伝えてください。
猫カビになったときに自宅でできる対策
猫がカビと診断されたときに自宅でできることは感染源との接触を防ぐことや、生活環境を綺麗にすることなどです。
動物病院での治療に合わせて自宅での対策も行いましょう。
感染源との接触を防ぐ
感染源となり得る外に出る猫や、野良猫との接触は感染リスクを高めるので避けましょう。
多頭飼育の場合、猫カビに感染している猫はなるべく隔離することをおすすめします。
可能な範囲で、移動も少なくできるとより良いです。
猫カビは動物間だけでなく、動物と人の間でも感染します。
感染している猫に触れたあとは手だけでなく、腕などもよく洗いましょう。
服などに着いた感染猫の抜け毛が、他の猫に着くことで感染が蔓延することもあるので注意が必要です。
また、感染している猫以外にも、感染猫の毛が付着していそうなものは感染源となります。
毛布やクッション、ブラシやバリカンなども感染源になる可能性が高いです。
生活環境を綺麗にする
生活環境を綺麗にすることも猫カビの対策として重要です。
皮膚糸状菌は生命力が強く、自宅内で1年間も生き残ることができると言われます。
抜けた毛も感染源になるため、掃除をしないと再び感染してしまいます。
掃除機や使い捨てシートなどで床を綺麗にし、消毒液を使用して掃除しましょう。
毛布やクッションなど洗えるものはなるべく塩素系の消毒液につけてから洗濯することをおすすめします。
免疫力の維持
猫カビの感染は免疫力の低下にも関係しています。
基本的に子猫など免疫力の低い猫で感染しやすい皮膚糸状菌ですが、免疫力が下がると成猫でも感染します。
免疫力維持のために日頃から以下のようなことに気をつけてみてください。
・ストレスの少ない生活環境
・適度な運動
・バランスの良い食事
人間も猫と同様、免疫力が低いと感染しやすいです。
子供や高齢者、治療中の疾患がある人などはとくに感染のリスクが高いため、感染している猫とのスキンシップは控えることをおすすめします。
まとめ
猫のカビと言われる皮膚糸状菌は、主に感染動物との接触でうつっていきます。
野良猫との接触や、外に出る猫の場合はとくに注意が必要です。
脱毛や痒みなど心配な症状がみられたら動物病院でみてもらいましょう。
猫のカビは人にも感染するため、人に赤みや痒みなどの症状が出た場合は人間の病院でみてもらってください。
皮膚糸状菌は主に毛に付着し、抜け毛も感染源となります。
一度症状が治っても、環境が綺麗になっていないと何度も再感染する可能性があります。
カーペットやブラシなど毛が付着しそうなものは全て綺麗に掃除しましょう。
「猫が脱毛していてカビかもしれない」とお悩みの際はお気軽にご相談ください。
大阪市城東区鶴見区の動物病院
城東鶴見どうぶつ病院