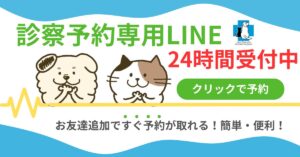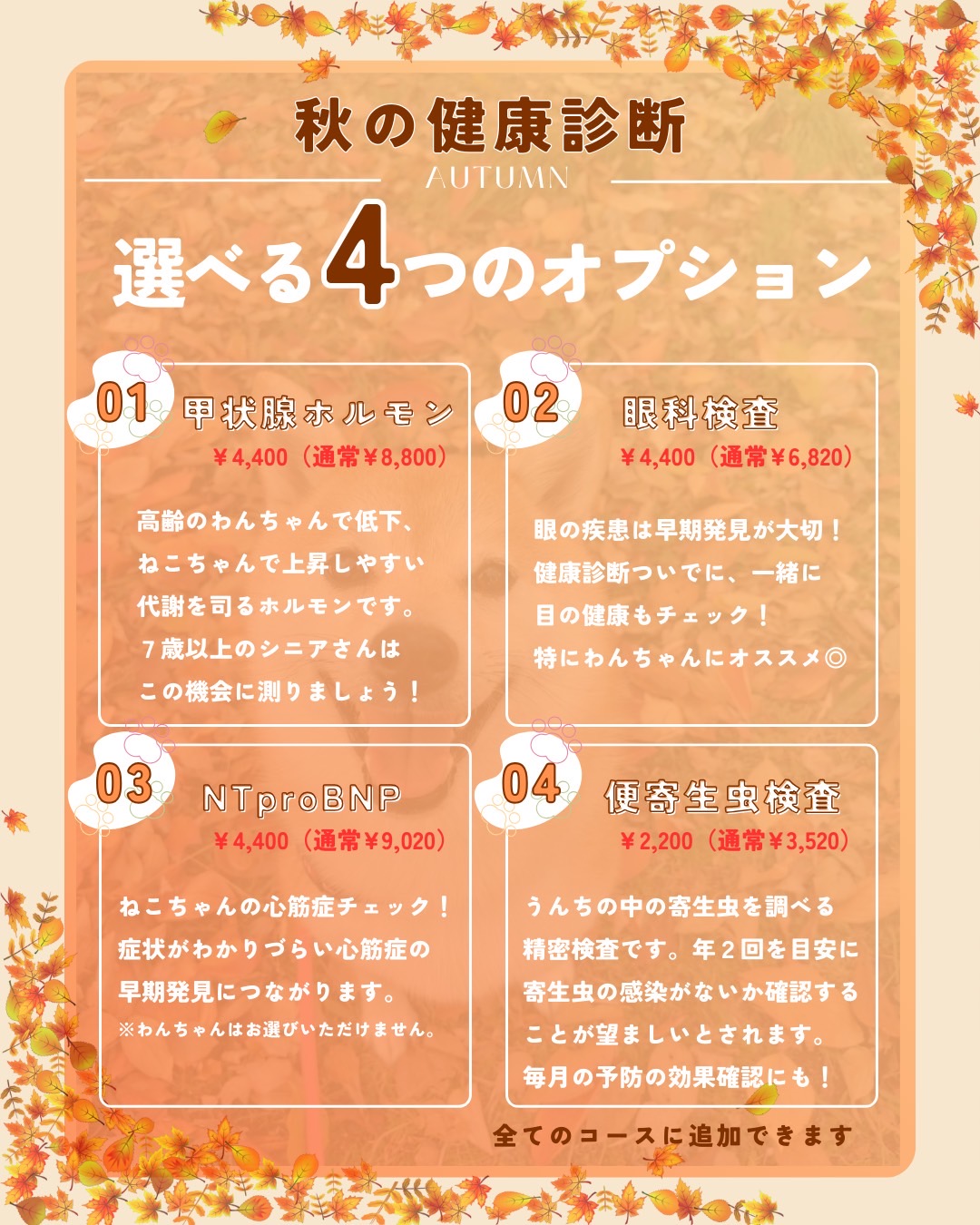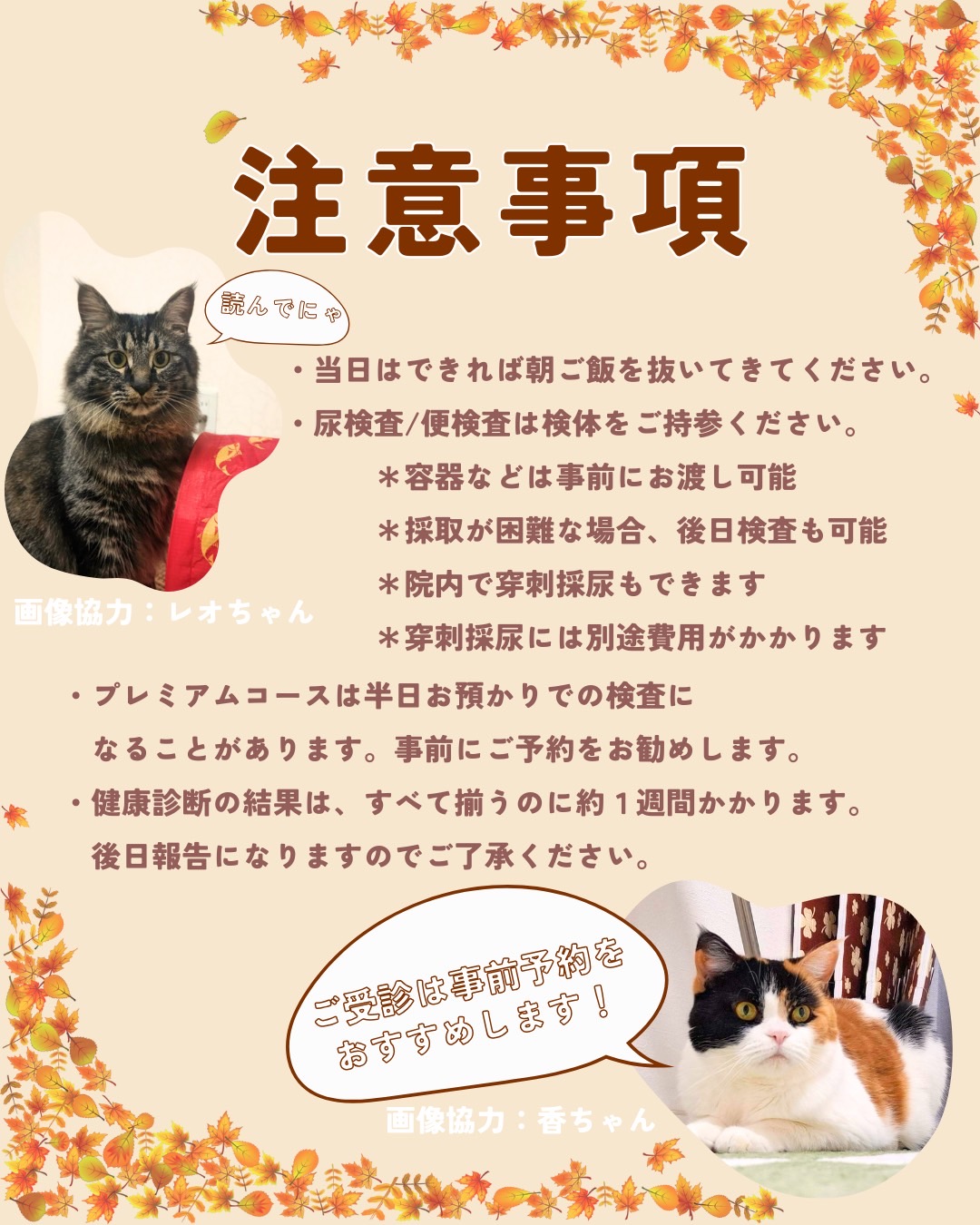「犬を飼い始めて去勢を検討している」
「犬の去勢を勧められたけどメリットはあるの?」
「なんで早めに去勢をした方が良いと勧められるの?」
犬を飼うと初めての手術が去勢になることが多く、このような不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
ぜひ最後までお読みいただき、犬の去勢を検討するときの参考にしてください。

犬の去勢手術ではなにをする?
犬の去勢手術は全身麻酔で行われるため、手術当日までに血液検査やレントゲン検査で麻酔をかけても問題ないかを確認する必要があります。
当日は絶飲絶食状態での麻酔となり、去勢手術で精巣が摘出され、生殖機能がなくなります。
精巣が正常な位置まで降りてきているかどうかによって手技は多少変わりますが、精巣が摘出されることに変わりはありません。
手術自体に問題なければ基本的に日帰りで終了するでしょう。
犬の去勢をするメリット
動物病院では一般的に若いうちに去勢することが勧められます。
これは、犬や飼い主さまにとってメリットがあるためです
健康面でのメリット
犬の去勢で得られる健康面でのメリットは、主に生殖器系疾患や会陰ヘルニアの予防などがあげられます。
▶︎生殖器系疾患の予防
去勢の最も大きなメリットは、精巣や性ホルモンに関連する疾患を予防できることです。
精巣腫瘍は中高齢のオス犬によく見られる疾患で、悪性の場合は他の臓器への転移リスクもあります。
去勢をすることで、このリスクを排除することができます。
また、前立腺肥大症の予防効果も期待できますね。
未去勢のオス犬は加齢とともに前立腺が肥大し、排尿困難や便秘などの症状が現れることがあります。
しかし去勢をすると男性ホルモンの分泌が抑制されるため、このような前立腺疾患のリスクを大幅に軽減することができます。
▶︎会陰ヘルニアの予防
会陰ヘルニアは、肛門周りの筋肉が弱くなることで腸や膀胱などの臓器が皮下に飛び出す疾患です。
この病気は主に未去勢のオス犬に発症し、手術が必要となる場合があります。
早期の去勢により、会陰ヘルニアの発症リスクを低下させることができるでしょう。
その他のメリット
去勢をすることで男性ホルモンの分泌が抑制されます。
それにより以下のような行動面の改善などのメリットも考えられます。
・攻撃性の軽減
・マーキング行動の改善
・望まない繁殖の防止
・長期的な医療費の削減
ただし、去勢のタイミングや性格・癖などによっては行動面が改善しない場合もあるため注意が必要です。
犬の去勢手術の注意点
犬の去勢手術には様々なメリットがある一方、気をつけなくてはいけないこともあります。
去勢後は太りやすく、手術自体も全身麻酔になるためある程度のリスクは伴うことになるでしょう。
去勢手術後は太りやすい
去勢後はホルモンバランスが変わるため太りやすく、体重管理が大切です。
犬の適正体重を維持するためには運動よりも食事での管理が重要となります。
去勢後はカロリーが抑えめのごはんに変更したり、ごはんやおやつの量を減らすなどの工夫が必要です。
手術には全身麻酔のリスクが伴う
全身麻酔は健康な犬でも100%安全と言い切ることは難しい処置です。
なぜなら病気が隠れている可能性があるためです。
若くして先天性疾患がある場合もありますし、犬種によっては構造的な問題や、特定の疾患になりやすいことなどから、病気でなくても麻酔リスクが高いこともあるでしょう。
事前に検査で隠れている病気を見つけることが大切です。
また、高齢になれば持病などでさらに麻酔のリスクが上がります。
基本的に若いうちの方が持病も少なく麻酔リスクが低いため、麻酔のリスクを考えても若いうちに去勢を済ませてしまう方がおすすめです。
まとめ
犬の去勢手術は精巣を摘出することで、健康面や行動面などで様々なメリットが得られます。
ある程度のリスクやデメリットはあるにしても、得られるメリットの多い手術です。
全身麻酔での手術になるため事前の検査は必要になりますが、比較的麻酔リスクの低い若いうちに終わらせてしまった方が良いでしょう。
犬の去勢を検討していてお悩みの際はお気軽にご相談ください。
大阪市城東区鶴見区の動物病院
城東鶴見どうぶつ病院